近年、「墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えました。核家族化や少子高齢化が進む現代において、お墓の承継に悩む方が増えているのが現状です。
そして、我が家もその一人です。
「先祖代々のお墓をどうすればいいのか」「自分たちの代で、お墓の管理が難しくなってきた」など、お墓に関する不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、現代のお墓が抱える課題から、墓じまいのメリット・デメリット、そして墓じまい後の多様な選択肢まで、あなたが後悔しないための情報をお届けします。
1. 現代のお墓の現状と課題
「お墓」と聞くと、故人を偲び、家族が集まる大切な場所というイメージがあります。
しかし、現代においてお墓は様々な課題に直面しています。
まず、お墓の維持管理費です。
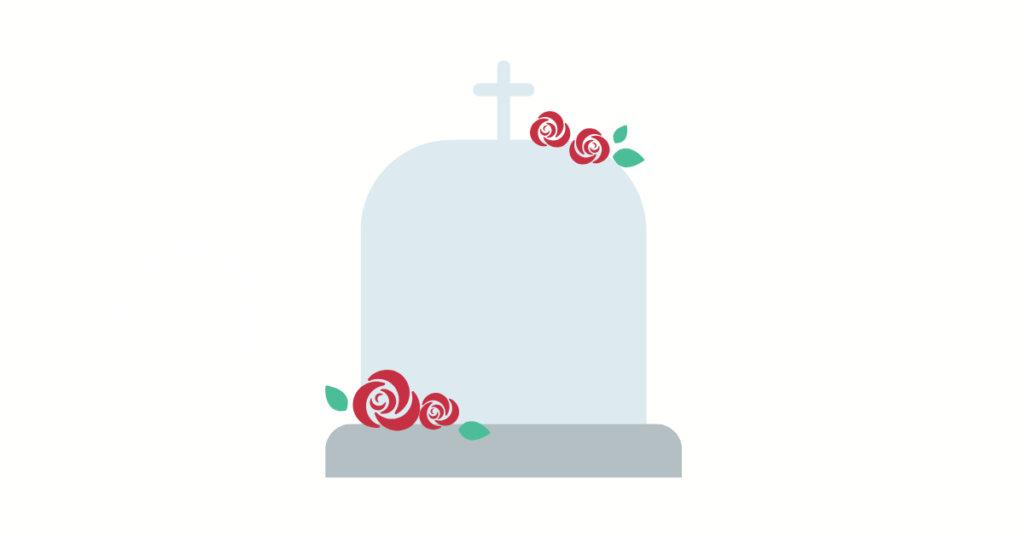
多くの場合、年間数千円から数万円程度の管理料がかかります。墓石の修繕が必要になれば、さらに費用が発生することも。これらは、お墓を所有している限り半永久的に続く負担となります。
そして、最も深刻なのが「承継者問題」です。
お子さんがいない、遠方に住んでいてお墓参りが難しい、経済的な負担が大きいなどの理由で、お墓を継ぐ人が見つからないケースが増えています。その結果、管理がされなくなったお墓は「無縁仏」となってしまうことも少なくありません。
昔ながらのお墓の形が、現代社会のライフスタイルに合わなくなってきているのが現状なのです。
2. 「墓じまい」とは?メリット・デメリットを徹底解説
こうした背景から注目されているのが「墓じまい」です。墓じまいとは、現在のお墓を撤去し、遺骨を取り出して別の場所に移すことを指します。
墓じまいのメリット
墓じまいには、以下のようなメリットがあります。
・経済的負担の軽減: 年間管理料や修繕費といったお墓の維持費が不要になります。
・精神的負担の軽減: 遠方のお墓参りの手間や、将来の承継者問題に関する悩みが解消されます。
・自由な供養の選択肢: 宗教や宗派にとらわれず、故人やご自身の希望に沿った供養方法を選ぶことができます。
・将来の不安解消: 子孫に管理の負担をかけずに済むため、安心して老後を過ごせます。
墓じまいのデメリット・注意点
一方で、墓じまいには注意すべき点もあります。
・親族との合意形成: 最も重要かつ難しい点です。親族の中には、墓じまいに抵抗を感じる方もいるため、事前に丁寧に話し合い、理解を得ることが不可欠です。
・手続きの複雑さ: 墓じまいには、役所への改葬許可申請など、複数の行政手続きが必要です。専門知識が必要となる場合もあります。
・費用が発生する: 墓石の撤去費用、閉眼供養(魂抜き)のお布施、そして場合によっては寺院への離檀料など、まとまった費用がかかります。墓じまい費用は数十万円から百万円以上かかることもあり、事前に相場を確認しておくことが大切です。
・供養方法の慎重な検討: 墓じまい後の遺骨をどこで、どのように供養するかをしっかりと考える必要があります。
3. 墓じまい後の選択肢:遺骨はどこへ?
墓じまいをした後の遺骨の供養方法は、現代において非常に多様です。ここでは主な選択肢とその特徴、メリット・デメリットをご紹介します。
永代供養墓(合祀墓、集合墓、個別墓など)
寺院や霊園が永代にわたり供養・管理してくれるお墓です。承継者がいなくても、無縁仏になる心配がありません。
合祀墓(ごうしぼ・ごうしばか)
複数の遺骨を一緒に埋葬するため、費用を最も抑えられます。一度納骨すると、後から遺骨を取り出すことはできません。
集合墓・個別墓
他の方と一緒に供養されるものの、一定期間個別のスペースで安置されるタイプや、永代にわたり個別のスペースが確保されるタイプもあります。費用は合祀墓より高くなります。
・メリット: 維持管理が不要、費用を抑えられる(特に合祀墓)、承継者問題が解消される。
・デメリット: 合祀の場合、後から遺骨を取り出せない。
樹木葬
墓石の代わりに樹木を墓標とする、自然に還ることをコンセプトにした供養方法です。公園のような開放的な雰囲気の場所が多いです。
・メリット: 自然志向の方に人気、費用を抑えられる場合が多い、承継者不要。
・デメリット: 場所によっては交通の便が悪い、個別のスペースがない場合もある。
納骨堂
屋内に遺骨を安置する施設です。ロッカー式、仏壇式、自動搬送式など様々なタイプがあります。
・メリット: 天候に左右されずお参りできる、駅近くなど交通の便が良い場所が多い、セキュリティが高い。
・デメリット: 永代使用料が高めの場合がある、使用期間が定められている場合もある。
散骨
粉末状にした遺骨を、海や山などに撒く自然葬の一種です。
・メリット: お墓を持たない選択、費用を抑えられる。
・デメリット: 一度散骨すると遺骨は戻せない、親族の理解が必要、散骨できる場所は限られている。
手元供養
遺骨の一部を自宅に置いて供養する方法です。ミニ骨壺やアクセサリーなどに加工して身に着けることもできます。
・メリット: 故人を身近に感じられる、いつでも手を合わせられる。
・デメリット: 全ての遺骨を自宅で供養するわけではないため、他の供養方法と併用することが多い。
これらの選択肢の中から、故人や家族の意向、そしてご自身のライフスタイルに合った最適な方法を選ぶことが大切です。

4. 墓じまいの具体的な流れと注意点
墓じまいは複雑な手続きを伴いますが、一般的な流れを把握しておくことで、スムーズに進められます。
1.親族との話し合い(最重要): まずは家族や親族に墓じまいの意向を伝え、理解と合意を得ることが何よりも大切です。
2.墓地管理者への連絡と離檀の相談: 現在お墓のある寺院や霊園に墓じまいの意向を伝え、離檀料などの相談をします。
3.新しい供養先の決定: 永代供養墓、樹木葬、納骨堂など、墓じまい後の遺骨の供養先を決め、契約をします。
4.改葬許可申請手続き: 現在お墓のある市区町村役場で「改葬許可証」を申請・取得します。新しい供養先の受入証明書などが必要になります。
5.閉眼供養(魂抜き)と墓石の撤去: 墓石から故人の魂を抜く「閉眼供養」を行い、その後、専門業者に墓石の撤去を依頼します。
6.遺骨の搬送と新しい供養先への納骨: 取り出した遺骨を新しい供養先へ搬送し、納骨します。
これらの手続きには、それぞれ費用や期間がかかります。特に、改葬許可証の取得や、閉眼供養・墓石撤去の手配には時間がかかることもありますので、余裕を持った計画が重要です。
まとめ:後悔しない「墓じまい」のために
「墓じまい」は、決してご先祖様をないがしろにすることではありません。少子高齢化やライフスタイルの変化に対応し、ご先祖様を大切に想う気持ちを未来につなげるための、現代における賢い選択肢の一つです。
ご家族でよく話し合い、メリット・デメリット、そして多様な供養方法を十分に理解した上で、後悔のない選択をすることが何よりも重要です。
あなたが納得のいく形で、故人を供養し、安心して未来を迎えられるよう、この記事が参考になれば幸いです。
《編集後記》
このままいけば、我が家の墓は次男一人が管理することになるでしょう。
そういったこともあり、墓じまいについていろいろと調べたわけですが
お墓参りの際、次男が言ったひと言が頭からはなれません。
『じーちゃん、ばーちゃんに見守られているようでホッとするな』
なるほど!
この気持ちを大事にしながら、どうするかを考えないといけませんね!!


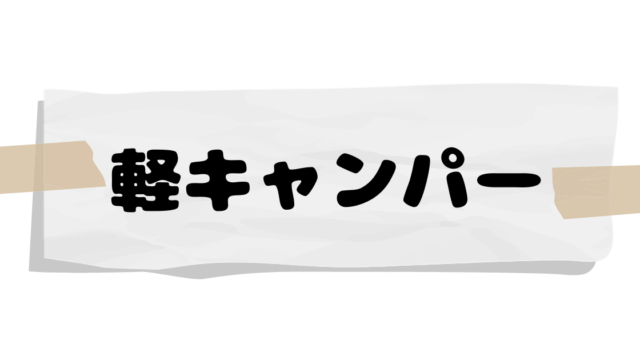

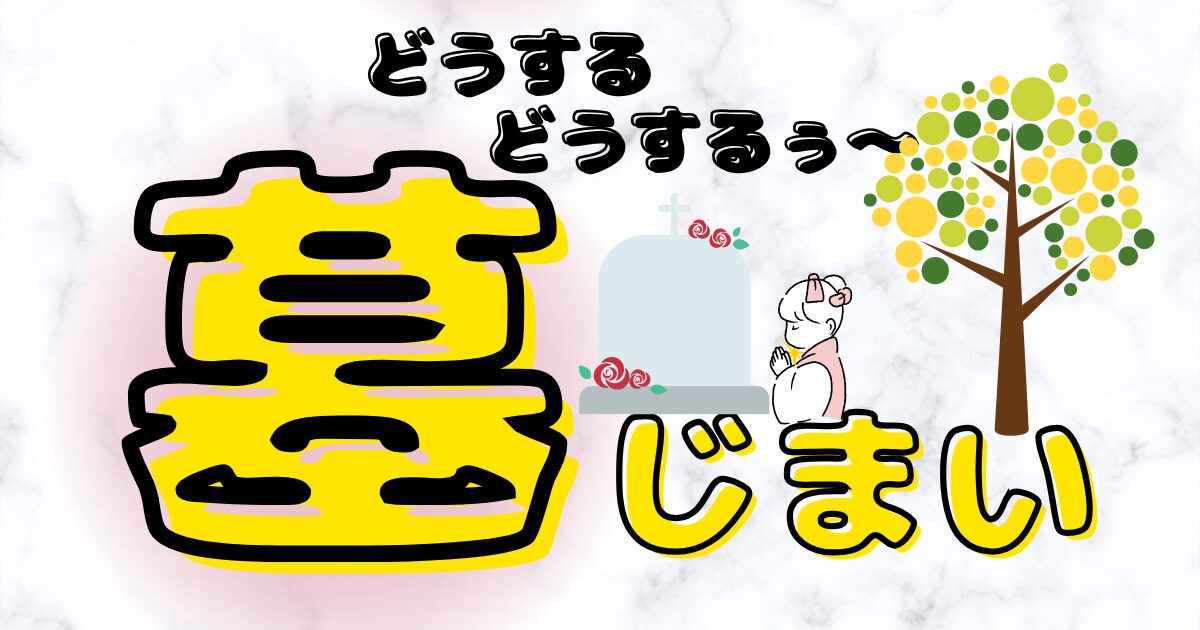
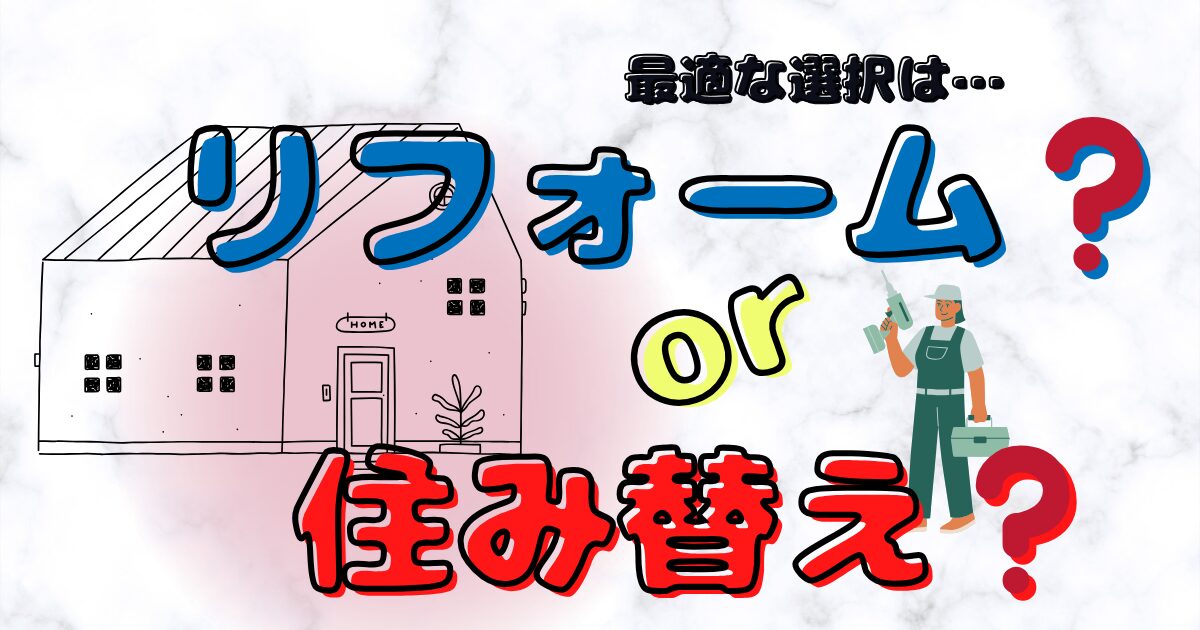

コメント